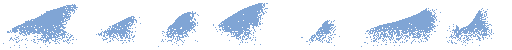
 僧ヶ岳 1885M 宇奈月コース
僧ヶ岳 1885M 宇奈月コース
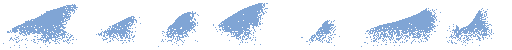
 僧ヶ岳 1885M 宇奈月コース
僧ヶ岳 1885M 宇奈月コース
宇奈月温泉のスキー場の上にあり、駒ガ岳へと続く稜線上。その昔は観音様の横から登ったように
記憶している。林道の工事中で小屋があった。残雪期の記憶だが、長くて苦しい登山の印象がある。
しかし近年は林道が魚津市の東蔵(片貝川)と繋がっているので案外簡単に山頂に立てるのだ。
林道の最高点で嘉例沢からの尾根上に烏帽子の登山口がある。1280M地点だ。
この林道を使うことで格段に登りやすくなった。危険な所もなく高山植物も豊富なので人気がある。
その先は北駒ヶ岳、駒ヶ岳と続く。北駒ヶ岳から宇奈月ダム湖畔の(栃の湯)へ下る尾根道もある。
その場合は車の回収に一台をそこへ回しておくことが必要となる。
| 2011年9月18日 | 2011年10月10日 | 2014年8月19日(火) | |
| 久し振りに仲間と | 連休の中日 | 体育の日 | 片貝川( 東又登山口) |
2014年8月19日(火)
2014年8月19日(火)
東又登山口から
以前、僧が岳の山頂にいて、この片貝側から登って来たお爺さんに出会ってから気になっていたルートである。
健脚ルートであと聞いていたのでいつかわ自分も経験したいと思っていた。
たまたま時間がるので思い切って出かけてみたが、暑さと気力不足バテバテで山頂まじかで敗退したのでした。
 |
片貝山荘の先に登山口があって数台の車が停車していた。 大方は毛勝岳の西北尾根に向かったものと思われた。 車を下流に方向転換して止めた。 上からの落石が予想されたので停車場所を気にしながら。 真上が登山ルートなのだ。 |
 |
こんな看板があった。 何度も通過しているが今まで全く目に入らなかった。 |
 |
7:30 登山口725M いきなりの急登で汗が噴き出る。 急斜面に岩と木の根が足場となっていて真下に自分の 車が見える。落石をしようものなら自損行為である。 |
 |
8:45 伊折山1370M 急登を終えると傾斜が緩み小さなピークに着いた。 しばらく休憩して出るがほぼ90度に折れている。 |
 |
10:21 成谷山1600M だらだらと登って行くと尾根に出た。 見晴らしがよい処だったが何しろ暑い。 雲が低く垂れこめてやたらと暑い。 風もなくもやっている。気力が萎えている。 先が見通せてい山頂が見えているが〜 気力を振り絞るように先へと足を向ける。 軽いアップダウンがある物の1時間くらいと思って出る。 |
 |
11:48 山頂の尾根で昼。 山頂がすぐそこに見え始めると ここでいいや〜とザックを下してビールを飲む これがまた〜すこぶる美味しかった! いつものラーメンをすすっておにぎりを食べた。 ザックに寄りかかって横になると睡魔が襲ってくる そのままちょっと休憩。〜〜 てな訳で山頂にに届かず下山しました。 今の時期は暑さで参るので秋ですね! |
2011年10月10日
体育の日
三連休であったのだが来店客があり、お仕事優先で店番。
それでも最終日には時間を作って出掛けた。予定を色々考えるのが面倒で先月来たばかりの僧ガ岳へ
再び向かった。紅葉を期待していつもより重いカメラと三脚を担いだ。だが今一の紅葉だった事もあり
結局一度も三脚を立てる事をしなかった。、手軽に紅葉の尾根を歩いただけのお散歩。
それでも爽やかな尾根道は気持が良かった。
 |
8:00 連休最後のこの日は、思っていたより車が少なかった。ただこの先の林道工事に入っている工事関係者と大型ダンプが激しく行き交うので。びっくりした。 |
 |
前回と違って黄色が鮮やかなトンネル |
 |
山は薄曇りで写真には向かない天気だった |
 |
それでも一部に綺麗な紅葉が眺められて満足 |
 |
ポカポカと暖かい日差しを受けてゆっくりと歩いた。 今回も前僧が岳をパスして迂回路を来た。 途中に以前の鉱山開発に使った物だろうか? 赤く錆びた鉄鋳物の残骸が所々に放置されて居る。 1800M地点から見た仏ガ原の紅葉。尾根に出ると開放感があって爽やかだ。 |
 |
山頂でゆっくり昼。 数組のグループが憩いで居るし、駒ヶ岳から戻ってきた人達も次々に到着して賑やかだ。 遠くに白馬の山が見えた。 |
帰りには宇奈月温泉街にあるセントに浸かり帰宅。このセント料金は350円。あまりに熱くて長湯出来ない
水を入れていたら、常連客だろうか?ぬるくなるから水を止めてくれないか!と古老の人から睨まれた。
登山客らしい数人と話しながら薄めて居たのだがやはり熱いのが好きな人が居るのだ!

2011年9月18日(日)
連休の中日に足慣らし
2011年9月18日(日)
仲間が穂高に行く。私は店番と家族の送迎があり定休日の日曜日しか空いていなかった。台風の影響で
前日(土)の予報では雨だったので、ゆっくりと起きた。ところが日が差し込んで青空が見えるではないか!
友人を誘ったが、前日の飲み会で体調不良だと言う。仕方なく1人で出掛けることになった。遅い朝飯を食って
家を出たのが9時過ぎ、途中コンビニに寄ってお茶とおむすびを買い込んでスタートするいつものスタイル。
 |
10:00 宇奈月に着くと、折からの観光客で車や人がびっしりだ。さすが連休だ。私はその間を縫って、林道へ向かう。くねくねと舗装された道路を行く、所々で平野を見おろすと高度感が有るのでびっくりする。 30分位の林道の最高点に烏帽子の登山口がある。しかし、出る前から暑さに参る!とにかく暑い! すでに林道は満車状態。折り返して片側へ駐車して出る。 写真はその駐車位置から黒部方面と海 |
 |
10:30 登山口の標識 標高が1280M地点 いさんで一度スタートを切ったのだが、水を忘れたので引き返す。 慌てる事も無いのだが、荷が軽いのでついついオーバーペースになる。 最初の40〜50分は息が上がって辛かった。登りに掛かるとペースを意識的落したのでようやく安定して楽になって来た。 |
 |
11:30 前僧ガ岳への分岐を直進して迂回路へ進むと 北側斜面はお花畑であった。 暑さに閉口していたが、このルートは日陰もあり風も吹き抜けるので気持が良かった。 |
 |
11:34 早い時期には残雪で危険な所も一部崩壊しているがロープがあり危険はない。 このルートはほぼ水平道で前僧ガ岳を迂回するので爽快な道だ。 |
 |
11:35 振り返ると、前僧ガ岳へ登る道がよく見える 谷を大きく迂回するので一件遠回りの様だが時間的にはこちらが早い。標高差にして100Mの登りが無いのである。 (実際には30M位の標高差であるが、一旦急登して下る前僧が岳ルートに比して、ほぼ水平に歩くので身体が楽である。) |
 |
11:37 日陰もあり、風もあり何となく身体も慣れてきた。 水平道からは白馬方面が見通せる。 |
 |
11:40 リンドウが林道に咲いている。 |
 |
11:43 北駒ヶ岳と奥に駒ガ岳が見えてくる。 |
 |
11:57 仏ガ原に着いた。 ガスが吹き抜ける強風の地形であるので 腰から上の植物が無い。 ぽつぽつと登る人、下る人の姿が見える。 |
 |
12:00 富山湾が一望出来た。風もあり癒しの空間だった。休憩を兼ねて、おむすびを一個食べる。 爽快な景色だ! |
 |
12:13 ひと登りで標識に着く、ここからの眺望がよい |
 |
12:20 山頂には8人位の人がいて食事タイムだった。車の数にしては少ない、大方は駒ヶ岳へ進んでいるに違いない。 私は日陰を探して、小道の陰に腰を下ろした。いつものラーメンを食べようとガスを出したがバーナーヘッドを忘れた事に気づいた。ザックの中を空っぽにして探してみたがやはり無かった。 いつもは、ビールとラーメンの定食だったのに 今回はビールも持参しなかった。何かリズムが違っていたようだ。 広場で焼き肉とビールで賑やかな人達の声を聞きながら、うらやましく眺めていた。 |
 |
12:36 仕方なくもう一個のおむすびを腹に入れて直ぐ下山する。山頂から駒が岳方面を撮る。 吊り尾根がよく見えている。 |
 |
12:42 |
 |
12:42 1800M付近の展望の良い所から 宇奈月ダムを撮る。 |
 |
12:52 戻りはさすがに余裕があるので様々な草花に目が行く。ゆっくり眺めながら下った。 |
 |
13:10 前僧ガへの分岐点 |
 |
13:17 ナナカマドの赤い実が日の光を受けて輝いている 秋の気配を感じる。 |
 |
14:00 登山口に帰る。やはり暑さがたまらない。 |
少し下った所にある、谷に冷気を伴った小川で身体をぬぐって生気を取り戻した。
ここにはこの小川が年中水が取れるので気持が楽だ。猛烈に冷たいので上部に雪渓が残っているのかも?
久し振りに仲間と
2008年7月22日(火曜日)
三連休の後、足慣らしに友人を誘って出掛けた。1280Mの烏帽子の登山口からのルート。
 |
さすがに平日の林道は空いていた。 宇奈月温泉からスキー場を過ぎてからが長い つづら折りの林道をぐんぐん高度を上げる。 8:30 烏帽子の峠にある登山に着いた。 既に標高は1200M以上の高さ。 路肩にある広場に車を停車し出る。 緩やかな傾斜の歩道と幾分強い傾斜が 適度にあるので、調子よく歩ける。 時々日光に当たると差すような暑さを感じる |
 |
10:09 谷沿いに山腹を切ったトラバースルートが雪渓で ふさがれているので迂回路が指示されていた。 尾根上の前僧ヶ岳へのルート。 かなり急な階段状の斜面だった。 そこをどうにか越えると見晴らしの良い 前僧が岳の上に立った。 |
 |
10:22 少し行くとご覧のような標識があった。 |
 |
その丘から下り始めると僧ヶ岳と下に仏ヶ原が見えた。 山頂はガスが早く流れ雲の中である。 |
 |
|
 |
10:28 仏が原ではニッコウキスゲの群落が華やかに 咲いていた。一面のお花畑だった。 ガスが吹き抜けるここは大変涼しい所。 見渡す限りに咲いている。 |
 |
シモツケソウが通路に沿ってポツリとあった |
 |
仏ガ原を振り返る。 日光が当たらないので救われる辛い尾根の登り 振り返るとダムが眺められた。 |
 |
10:45 通路の曲がり角にひっそりとあった。 その先が山頂かと思っていたらもう一つ先に 小山があった。 |
 |
10:54 一旦下り登り返すと、猿の群れと鉢合わせ 登山道を空けて笹藪をザワザワと波打たせて 去って行く。 見送りながら少し登ると山頂に着いた。 あいにく四方の景色は無い。高曇りのそらは ジリジリと暑い。 しばらくすると地元の小学校の先生達が遠足の 下見と称して登ってきた。 来週に登山計画があるらしい、ご苦労様です。 |
13:00 下山開始
快調に下る。ガスの中に風が涼しい、それでも玉のような汗が滴となって落ちて行く、何しろ暑い。
14:30 登山口着
車に着くとまず靴を脱ぐ。それからグレープフルーツだ、実に美味しい。
保冷剤を首筋に当てると気が遠くなるような快感だ。
すーっと火照った体を冷やす。
車で下りの途中に小川を見つけて流れに手を入れる。
あまりの冷たさに心臓が一瞬手で捕まれたようにキューと縮む。
身体を手ぬぐいで拭うとやはり冷たさでシャキッとする。
それ程体温が高いのだった
先ほどの山頂で会った猿の群れが道路を横切って行く、大きな群れだった。
公共浴場の宇奈月温泉が休み(定休日が火曜日)なので
対岸に渡り栃の湯に向かう。ダム湖を望む露天風呂は開放感があって良いのだが
何かしら情緒がない。
着替えてさっぱりして帰宅。
