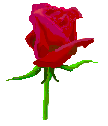
| Lovely Life のために | |
|
| 愛ってなんだろ〜 | HomeMenu ← | CONTENTS ← |
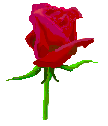 |
|
| ほんとうの自分 | |
| 1 序 | |
| 2 自分がいる、相手がいる(あるいは分ける) | |
| 3 比べる | |
| 4 精神について | |
| 5 身体について | |
| 6 無境界 |
| 1 序 | |
| 我々の意識が仏教のいう「色の世界」(この世界に 私がいて あなたがいて、実在の私と 実在のあなたが出会う―という具合に捉えたときの世界像)(さらに、話の角度を少し変えると、ここに一匹の牛がいるとする。その牛にはその牛の、この世界の見え方が、あるだろう。一つの世界像が、あるだろう。その牛が 存在する ということは、その牛の内界が一つの世界像を作り上げ、その世界像(牛の外界)と牛が相互作用し合っている、ということである。もし、色の世界しか見ないならば、牛は・・・ただの牛、である。ミルクを絞るなり、食べてしまうなり、好きにすれば、それでオシマイである。牛は、人間に益する動物、家畜である。虎は、猛獣。猫は、ペット。私は、ヒトで、日本人で、大学院生で、男性・・・というような、「意味の世界」が始まる世界。しかし、実際、「意味の世界」と無縁なのは赤ちゃんだけで、マトモな大人は全員、この世界像と共に生きているし、この世界像がなければ、生きていけない。しかし、その枠にはめ込まれていては、窮屈で不自由な思いをする)にある時(おおかたの時そうなのであるが)、そこでは、「自分」と「自分以外」が分かれている。自他の区別があるのだ。であるから、「自分」が「他なるもの」と出会う、ということが生じる。その出会い方には、いくつものパターンがあるが、大別すると、自他の境界線を無くしていく出会い と、その境界線をより堅固なものにしてしていく出会い方 である。 |
| 2 自分がいる、相手がいる(あるいは分ける) | |
|
まず、自他の境界線は在る として、自他を分離分割している、(我々の通常の)心の姿勢から見ていこう。 自分がいる 相手がいる・・・という認識方法をとったとき、私たちは、まず真っ先に、何を知りたくなるか。たとえば、無人島でばったりとヒトと遭遇した と想定すると、あるいは、異星人が大挙してこの地球にやって来た と想定すると、我々がまず知りたいのは「それが敵か味方か。つまり、自分はその者と共に、安心して居られるか否か」である。我々に攻撃危害を加える者なのか、それとも、我々にとって友好的な者たちであるのか、それが第一の関心である。 自他を分割する認識方法から生ずる、この「敵か味方か」式パターンは、動物に出会っても(危険な猛獣か、あるいは食用になるか、ペットになるか)、植物に出会っても(毒性があるか、あるいは食用になるか、木陰となるか、木材として利用できるか)、人間に出会っても、(その人は自分になにをもたらすか)、敵(自分にとって都合の悪い相手)か、味方(自分にとって都合の良い相手)か、に「分ける」パターンは変わらない。しかし、いったん味方だと認定できた相手でも、それが恒久不変の関係に固定されるとは限らない。相手の意向は永久に変わらないという保証は、無い。婚姻の儀式で、婚姻者双方が永遠の愛を誓い、かつその誓いを公的に表示すべく、指輪等をはめ合うのは、「生涯の味方」の保証を取るためであろう。家族肉親を(赤の他人たちより)特別視しているのは「安心していられる味方」への欲求から生じているのだと考えることができる。また、世界中に各種様々の「党派」が結成されているのも、味方同盟への欲求の顕れであろう。 |
| 3 比べる | |
|
我々は、自他の境界線を引いたときから、「他なるもの」に出会うと、「そのもの」が自分にとって好都合のものか、否か を分けつづけているのであるが、この心的作業のほかに、敵であるとすれば、どちらが強者か、敵味方の区別があいまいならば、どちらが社会的順列は上位か という、「比べる」仕事が残っている。 地上と人類を国家群に分けて、いずれが大国であるか、比べつづけ、競いつづけている。各国の貿易収支、GNP、オリンピックが始まればメダル獲得数、・・・。一国内では、企業間競争であり、私とあなたでは、どちらが社会的に上位であるか(どちらが先に頭を下げるか)、どちらが美人(美男)であるか、どちらが、つまりは、価値ある人間なのか。 我々は、分けて、比べて、競い合うことが、生きる上での心的習慣になっている。この心的習慣がある限り、私たちが強者となることを欲し、弱者に脱落することを恐れるのは、当然の帰結である。 しかし、なぜ我々は、この心的立場に自分を据えつけてしまうのか、そこに縛りつけられ、そこから解放され得ないのか、と言えば、それは、私たちを「私」たらしめている意識(わたし感覚)が、個人個人に宿っているからである。「わたし」という意識=わたし感覚 が、「私」という意識野に、個別(個的生命体ごと)に宿っているからである。 すべての個的生命体(生物)は、本能としてその個的生命体を大切にするわけであるが、ヒトは知能あるゆえに、単に「大切にする」だけでなく、この「わたし感覚」(生命性)の永続を思念するようになる。永続を念じる とは、つまり、常にいつまでも若く強くあることへの願望であり、同時に、老・病・死におそれをいだくことである。このおそれから解放されるために(同時に、あくことのない思念・願望の連環から解放されるために)、古来から、聖職者たちは、自他の境界線を、放棄すること、自他の区別心の基となっている「私=人間が、わたし意識の永続を念じること」そのものを、放棄すること、を主張している。個的生命は大切にせよ、ただし、その永続を念じることは放棄せよ。これが賢者の主張である。 |
| 4 精神について | |
|
次に、「自分」が「自分以外」のものと、境界線を無くしていく方向で出会う心の姿勢について、見ていきたい。 自他の区別といい、自他一如(一如=真理の現れ方はちがっても、本は一つで分けへだてがないこと)(無境界)といい、それは、我々一人ひとりの精神内部の出来事である。では、精神 とは何か?最も基本的なところに視点(あるいは内なる感受性)を据えると、精神とは「自分のことを 自分であると感じているもの」である。我々一人ひとりに「わたし」意識をもたらしているもの、そのものである。あなたが、あなた自身のことを、「自分だ」と感じつづけているもの(知りつづけているもの)、それが無いと、あなたは、あなたでなくなる。それが、我々一人ひとりの、精神そのもの である。そして、このものの特性を仏陀は、般若心経において、不生不滅 不垢不浄 不増不減 と看破している。「自分のことを 自分であると感じつづけているもの」は、(それに思いを馳せると、ただちに了解できることであるが)、いつから生じたというものではなく、いつ滅するというものでもなく、汚れることも清まることも、増えることも減ることも、あり得ないのである。それは、不可視であり無形であり、人為的に手の届かぬものである。人為的に一切の操作ができぬものであるから、それを(人為的に)分割するとか、所有者を明らかにするとか、一切できない。それどころか、それ(自分を自分であると感じつづけているもの)を、我々は、接続させることも停止させることも、出来ない。ただ、それ(精神そのもの) は、感じて味わうことができるのみである。それ を充分に感じ味わったとき、我々は、それ はあたかも、水中にある一個のコップのようなもの であり、無辺無定型に遍満する おおもとの精神(水の全体) が、「わたし」という一領域(一つのコップ)に注入されていること を感受する。おおもとの精神 が、一人ひとりの個的生命体に注入されている結果、私は私としてあり、あなたあなたとして(一日おきに入れ替わったりせずに)この世界に居つづけているわけである。 そして、私たちは、ほとんどの時、この おおもとの精神 が注入されていることを、忘れている。不思議なほど忘れつづけて、生きているのである。 |
| 5 身体について | |
| たとえば、我々が、自分の身体をその五体全部の隅々まで感じようとすると・・・ 目をつむり、立っていても寝ていてもいいのだが、不動の(動作しない)姿勢を保ち、体内の緊張をゆるめる。すると、自分の身体の全部を、感じることができる。通常、こんなことはしない。通常、我々は、自分の身体の全体性など忘れて、立ったり座ったり、歩いたり、包丁を使ったり、ワープロを打ったり、している。することの目的が、主で、それを行う身体は、従である。駅まで10分間で歩くこと(10分後には駅に着くこと、つまり、動作行動の目的)が主で、身体そのもののことは、ほとんど無自覚である。つまり、身体(その動作)そのものについての覚醒は、ない。身体がなにをしているか知らずに、ただ動いている。しかし、身体を使うことの専門家(舞踏家・演技者・スポーツマン、あるいはトビ職を始めとする職人、等の人々)は、「いま、身体がなにをしているか、完璧に知りつつ動作すること」、すなわち、自己の身体性について覚醒しつつ所作動作することを目指し、彼らのうち、あるしきいを越えた高水準の者たちは、それを達成している。身体動作について覚醒しているということは、彼らの自己と身体動作が分割分離していない、ということである。そこには、自己と身体動作の一体一如性が、認められる。 |
| 6 無境界 | |
|
我々が、自分の精神の全体性、つまり 精神そのもの を、隅々までくまなく感じようとすると、必ず、不生不滅 不垢不浄 不増不減の おおもとの精神(自分を自分であると感じさせているものの元) に行きつくだろう。それは 無無明 亦無無明尽 乃至無老死 亦無老死尽 無苦集滅道 無智亦無得 迷いなく、(始めから無い)迷いの尽きることもなく 老いも死もなく(始めから無い)老いや死が尽きるはずもないところに至り そこには苦しみは(始めから)存在せず (存在しない)苦しみの原因は、あるはずがなく (存在しない)苦しみを減らすことも、減らす方法もあるはずがなく (なに一つ)知ることも得ることもないものである。 そして私たちは、身体につてと同様、精神についても、それとの一体一如性を忘れて生きている。精神につての自覚も、覚醒もないままに。 「自分」と「自分以外」を分けることは、精神の「はたらき」である。認識とは、そこから始まる。赤ん坊の、原初的混然一体世界像から、まず「自分」と「自分以外」を分割認識することにより、人は人たりえる。しかし、「自分」と「自分以外」を分けるところから同時に、私たちは、「自分を自分であると感じつづけているもの、精神そのもの」を忘れるのである。 そこで、身体動作についての一体一如性具現者たち(秀でた舞踏家や熟練の職人)に倣って、精神と自己との一体一如性を具現しようとするとき、我々は、瞑想など内なる感受力を要求される。瞑想などの中で、あたかも身体の専門家が全体性を感じとるように、我々は、「自分を自分であると感じつづけているもの、すなわち、我々の精神そのもの」を再び奪回し、そうして我々は、次のことを知る。 自分と自分以外を分別したところから生じている、一切のものは、「精神のはたらき」に過ぎないことを。 精神のはたらき と、精神そのもの とは、まったく別のことがらである、と知る。たとえば 自分は一人である、も 自分は自分の力で生きなければならぬ、も 自分の人生は自分のものである、も 自分という人間(人格)は自分のものである、よって 自分の物(自分に与えられた物)は、自分の所有物である それは、他人の物と比べて、多いか少ないか、美しいか醜いか それは価値ある物か、価値ある物ならば、 コワされぬように盗まれぬように、大切にしなければならぬ、も ― これら一切は、「精神のはたらき」に過ぎないこと、を知る。前途の身体になぞらえると、これら一切は、立つこと歩くこと、包丁を使うこと、ワープロを打つこと、に相応することを、知る。 身体のすること(駅まで10分間で歩くこと・目的)が主となり、それを行う身体そのものが従となったのと同様、通常の我々は、精神のすること(はたらき)― たとえば、私は独りぼっちである、や、私はあの人より美人であるか美男であるか、等々の精神の働き ― を主とし、精神そのもの を従としていることを、知る。 このように、精神そのもの より、そのはたらきを優先させたまま、「自分」が「自分以外」すなわち他者、と出会うと、我々は、「分け、較べ、競う」精神のはたらきに、どこまでも埋没していく。 他者と出会っているときに、他者と出会っているという認識を持ったまま(すなわち色の世界・自他区分の世界にありながら)、いま自分がなにをしているのか 完璧に知りつつ出会うとすると・・・。 そのとき、我々は 私を私と感じさせているもの(おおもとの精神)と その人をその人と その人に感じさせているもの(おおもとの精神)は 分かちがたく「一つ」であること を知る。 それが、自他・無境界・共生感の始まりである。 |
| 自分探しの旅 |
| Top of this page |
|
akihito |
|
