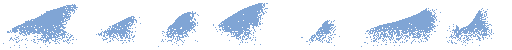
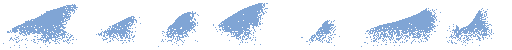
 越知山612.8M
越知山612.8M
| 2024年12月2日 | |
| 晩秋の仏道 |
越知山(おちさん)は、福井県福井市と、丹生郡越前町の境にある標高612.5mの山。
古くから白山、日野山、文殊山、蔵王山とともに越前五山の一つに数えられてきた。
泰澄が幼少の頃夢のお告げにより、青年まで修行したと伝わる北陸最古の修験霊場として伝わる。
山頂は越知神社、奥之院
2024年12月2日
2024年12月2日
晩秋の仏道
 |
登山口は小川越知山登山口から尾根を辿る 一合目から十合目まで標識があり時間確認やペース配分が出来る。 概ね 良い休憩ポイントだった。 先に進むほどアップダウンが大きくなり。8合目からはペースダウウン |
 |
奥糸生多目的集会施設 登山口には公民館がありその裏には広い駐車場があった。 茶色のドアがトイレ(和式・水洗)です。 朝早く着いた6時頃は一面の深い霧に覆われて周辺が見えなかった。 |
 |
8:00 霧が晴れるのを待って出発。 登山口は公民館の横にあり、修行道コースを行く。 ちょうど公民館(駐車場)の裏山へ登ってゆく感じだった。 しばらく、薄暗い杉林を行く。 |
 |
8:27 2合目に出ると、林道が交差しており、跨いで、鉄梯子を登る。 急傾斜なので注意して登る。 急な斜面で地図で見ると、標高差50m位の小さなピークを乗り越すルートだった。 結局その林道は山を迂回して再び登山道に合流するのである。 ※多くの履歴を見るとこの小山を通過してる事例が少ないので足場が悪い 最初で最後の通過で現場確認!! (お勧め:2合目から3合目までは林道を行く迂回ルートのほうが楽である。) 帰りは迂回ルートで戻った。 |
 |
8:54 軽いアップ、ダウウンを繰り返しながら快適にブナの尾根道を行く。 要所要所に目新しい石仏があった。 |
 |
8:58 四合目を過ぎたあたりから、目指す山頂が見えた。 未だはるか遠くに見える。 |
 |
9:00 5合目辺りに切り開いた様な展望箇所があり、雲海の景色を見ることが出来た。 |
 |
9:14 唯一ここだけに、残っていた紅葉のトンネルがあった。 |
 |
9:15 木の実谷コースに出会う。 登下山が可能だが、上級者向け~と書いてある。 |
 |
9:23 独鈷水 石仏が多数祭ってる。 近くに水場がある、 9:45 八合目 いよいよ最後の登り、長かった。 真っすぐな溝になった坂道。 落ち葉が、溝に堆積しており、急な斜面では良く滑る。 足の太ももが攣りそうになったのでペースダウン。 1人だとどうしても休憩を取らなくて、ペースが速いのだ。 |
 |
10:03 |
 |
10:06 登りきると、右手に神社があった。 木の鳥居で珍しい。 まずは、越知神社に参拝。 ここには裏側から車道が来ていたのだ。 越知神社を後に、下に見えている駐車場方面に向かう。 左手にあるのが殿池。やや左奥の建物がトイレ。 右奥に駐車場があった。 未だ奥のほうに参道が続いている。 多くの小さな石仏が納めてある建物の前を通過。 ガラス越しに綺麗に並んでこちらを見ている。 皆、願いを込めて奉納されたものだろう。 さらに10分位歩くと石段の上にあった。 |
 |
10:23 山頂の奥の院に着いた。 やや風があるが見晴らしは良い! まずは参拝 小銭を賽銭箱に入れ思い切り鈴を鳴らした。 |
 |
越知山612.8m |
 |
そこから神社が向いている方向を見る。 遠くは白く輝く白山辺りが見えている。 そこまで全く人に出会わなかった。 |
 |
10:38 一旦戻って案内板を見て、食事場所を探す。 風があり冷やされるので、日当たりで風を避けられる所を探してみた。 結局、電波塔の陰でゆっくり食事を始めた~が その直後、車が登ってきて、3人の作業員が電波塔のフェンスを開けて作業を始めた。 この山で初めて出合った人が作業員だった。 |
 |
10:42 結局ここから歩いて10分位に展望台が有ったのだが、早とちりでここが 展望台と勘違いしてしまったのだった。!残念! |
 |
11:00 電波塔の横に小さな社があって、そのそばにカワユイ石仏があった。 思わぬ出合いに、私もひざまずいて手を合わせていた。 すごく印象に残ったお地蔵様だった。 11:20頃 下り始めると、トレイルランナーが追い越して下って行った。 9合目の坂道に掛かると、4名の登山者が登って来た。 声を掛けると皆同じ年ごろの年配者だった。 一旦顔を上げてくれたが、下を向いたまま黙って登って行った。 ここが一番苦しい所だった。 12:20 木の実谷コースに戻る。しばらくここを下ろうか?と迷った! ~が長い林道歩きを思いやめた。 下山時、3合目過ぎの林道に出て、2合目まで林道を迂回した。 12:59 登山口に戻る。 |